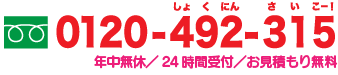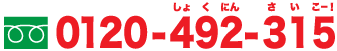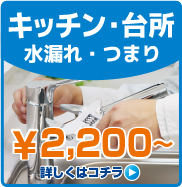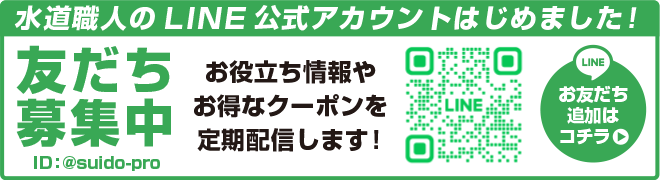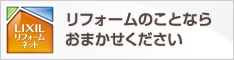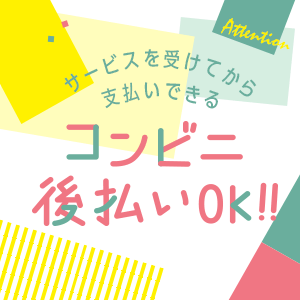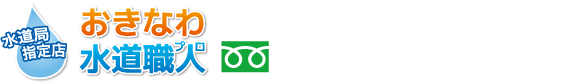水のコラム
白く染まる沖縄の海|海水温上昇とサンゴの白化被害【水道職人:プロ】
エメラルドグリーンに輝く沖縄の海。
その美しさを支えているのは、海の中で色とりどりに咲くサンゴたちです。
まるで海中の花畑ともいえるサンゴ礁は、まさに沖縄の宝物と言える存在ですよね。
ですがこのサンゴに今、深刻な「異変」が起きています。
年々上昇する海水温の影響もあり、サンゴが真っ白になってしまう「白化現象」が大きな問題になっています。
環境による問題と思いがちですが実はこの危機、私たちの日常生活とも深いつながりがあることをご存知でしょうか。
普段何気なく使っている日焼け止めや洗剤、お風呂やキッチンから流れる生活排水…こうした身近なものが、実は美しいサンゴ礁に思わぬ影響を与えているんです。
今回は、沖縄のサンゴが直面している現実と、私たちにできることについてまとめてみたいと思います。
目次
記録的な海水温上昇でサンゴが悲鳴をあげている
2024年8月、沖縄の海水温は観測史上最高の30.9℃を記録しました。
これは過去10年間で最も高い温度なんです。
たった1〜2℃の違いでは?と思われるでしょうが、サンゴにとってこのわずかな温度差は、まさに生死を分ける大問題。
サンゴって実は、クラゲなどと同じく「動物」なんです。
体の中に「褐虫藻(かっちゅうそう)」という小さな藻類を住まわせて、お互いに助け合って生きています。褐虫藻は光合成でサンゴに栄養を提供し、サンゴは褐虫藻に住みかを提供する…まさに理想的な共生関係と言えます。
ところが海水温が30℃を超えると、この素晴らしい共生関係は突然破綻します。
高温によるストレスで褐虫藻がサンゴから逃げ出してしまい、栄養を作れなくなったサンゴは白い骨格だけが残る「白化現象」を起こしてしまうんです。
その結果、日本最大のサンゴ礁「石西礁湖」では、現在、健全なサンゴはわずか1.4%ほどしか残っていないと言われています。
98%以上のサンゴが何らかの被害を受けているという、まさに危機的状況なんですね。
観光業と漁業への深刻な打撃
サンゴ礁の劣化は、沖縄の経済にも大きな影を落としています。
観光業は沖縄県の基幹産業で、多くの人々の暮らしを支えていますが、美しい海を求めて訪れる観光客の減少と、魚たちの住みかの消失により、地域経済全体が深刻な打撃を受けているんです。
観光収入が3割も減少
沖縄といえば、透明度抜群の海でのダイビングやシュノーケリングが大人気ですよね。
でも、サンゴ礁の劣化とともに、観光客の足も遠のいているのが現実。
2019年には約8,590億円もあった国際観光収入が、2023年には5,390億円まで落ち込んでしまいました。
実に37%もの減少です。
3,200億円という巨額の減収は、多くの観光関連業者や従業員の方々の生活に直接影響を与えています。
サンゴ礁は「海の熱帯雨林」と呼ばれるほど、たくさんの海の生き物たちの住みかとなっています。
色彩豊かな魚たちが泳ぎ回る光景は、まさに沖縄観光の目玉でした。
そのサンゴが失われることで、海の魅力そのものが薄れ、ダイビングやシュノーケリング目当ての観光客も減ってしまっているわけですね。
漁師さんたちの新たな挑戦
サンゴ礁の減少は、漁業にも少なからず悪影響を与えています。
サンゴ礁は魚たちの産卵場所や隠れ家として重要な役割を果たしているため、サンゴがなくなると魚の数も当然激減してしまいます。
実際に、ハタ類の水揚げ量は20年前と比べて3割ほど減少、ブダイ類に至っては4割に及ぶと言われています。
代々漁業で生計を立ててきた漁師さんたちにとって、これは深刻な問題ですよね。
ただ、そんな困難な状況の中でも、希望の光も。
恩納村の漁師さんたちが主体となり、魚を獲るだけでなく「サンゴを育てる」という新しい挑戦を始めているんだとか。
現在では24,000株ものサンゴを大切に育て、海に植え戻す活動を続けています。
「海を守ることが、結局は自分たちの生活を守ることにつながる」という思いで、日々努力を重ねておられるそうです。
私たちの生活がサンゴに与える影響
意外に思われるかもしれませんが、遠い沖縄の海で起きているサンゴの白化現象は、私たちの日常生活と密接に関わっています。
海水浴で使う日焼け止めから、毎日使っている洗剤まで、身近な製品がサンゴ礁に思わぬ影響を与えていることはあまり知られていません。
日焼け止めの意外な落とし穴
夏の沖縄旅行といえば、まず思い浮かぶのが日焼け止めですよね。
強い紫外線から肌を守るために欠かせないアイテムですが、実は多くの日焼け止めに含まれる「オキシベンゾン」という成分が、サンゴにとって非常に有害だということをご存知でしょうか?
研究によると、例えば学校などのプール6杯分もの大量の海水に、たった1滴の日焼け止めが混ざるだけで、サンゴの白化やDNA損傷が起こることが分かっています。
沖縄の人気ビーチでは実際に安全基準の数十倍もの濃度でオキシベンゾンが検出されており、深刻な環境問題となっています。
海水浴を楽しむ多くの観光客が使う日焼け止めが、結果的に美しい海を傷つけてしまっているのは悲しい現実ですよね。
家庭排水が海を汚している
もう一つ見過ごせないのが、私たちの家庭から出る生活排水の問題。
お風呂やキッチンで使った水は、下水処理場を通って最終的に海に流れ着きます。
実は、家庭用洗剤に含まれるリンや窒素は、海に流れ込むと藻類を大量発生させる「富栄養化」という現象を引き起こします。
この藻類がサンゴの成長を阻害し、さらには海中の酸素を奪ってサンゴを窒息させてしまう原因にもつながるとされています。
また、普段何気なく使っているシャンプーや石鹸に含まれる化学物質も、サンゴの健康に悪影響を与えることが科学的研究で明らかになっているんだとか。
意外に思われるかもしれませんが、水は巡り巡って必ず海にたどり着くということを忘れてはいけません。
今日からできる海を守るアクション
美しい沖縄の海を未来に残すために、私たち一人ひとりができることから始めてみませんか?
まずはその第一歩として、日焼け止め選びから始めてみませんか?
「reef safe(リーフセーフ)」と表示された製品や、酸化亜鉛・二酸化チタンを主成分とする日焼け止めなら、サンゴに害を与えません。
少し値段が高いかもしれませんが、美しいサンゴ礁を守るための小さな投資だと考えてみてください。
また洗剤選びも重要なポイントです。
「リン酸塩フリー」や「生分解性」と書かれた製品を選ぶだけで、海への負担を大幅に減らすことができます。
重曹やお酢といった自然素材を掃除に活用するのも効果的ですね。
小さな行動の積み重ねが、きっと大きな変化を生み出すはずです。
そして多くの人が同じ気持ちで行動すれば、さらに大きな変化に繋がります。
海とサンゴ、そして私たちが共生できる未来を作るためにも、ぜひアクションを起こしてみてください。
監修者

主任
和田 大輝
《略歴》
水道メンテナンスの第一線で活躍する和田大輝は、公益財団法人給水工事技術振興財団によって認定された給水装置工事主任技術者です。
私は国家資格としての優れたスキルと専門知識を有しており、給水システムにおける高度な技術力を誇ります。
当コラムでは、給水工事における主任技術者の視点から、水回りのトラブル対応のアドバイスや家庭で実践可能な応急対応等にについて解説しています。
保有資格:給水装置主任技術者
沖縄のトイレのつまり・水漏れは、水道修理の専門店「おきなわ水道職人(沖縄水道職人)」
名護市 国頭村 大宜味村 東村 本部町 今帰仁村 恩納村 宜野座村 沖縄市 浦添市 宜野湾市 うるま市 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村 西原町 金武町 那覇市 糸満市 豊見城市 南城市 南風原町 与那原町 八重瀬町
その他の地域の方もご相談ください!